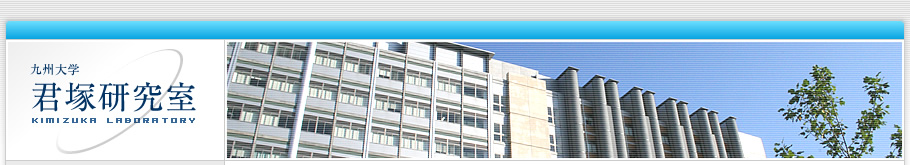福岡市西区元岡744番地
ウエスト3号館8階
九州大学大学院工学府
物質創造工学専攻群 応化分子教室
君塚研究室
TEL.092-802-2832 FAX.092-802-2838
研究概要
自己組織化に基づく“分子システム化学”の創成をめざして
分子の自己組織化を利用して分子間相互作用やナノ構造を制御し、システムとしての機能を導く“分子システム化学”は、次世代の科学として期待されています。私たちの研究室では、有機分子、生命分子、金属錯体、金属酸化物などの多彩な分子・ナノマテリアルを構成素子とし、それらの自己組織化現象に基づく分子システム化学の開拓 を目指しています(Figure 1)。

Figure 1 4つの研究キーワードと境界領域
有機分子(青色)、金属錯体・ナノ粒子(黄色)、生命分子(紫色)、ソフトイオニクス(緑色)の4領域ならびに、その境界領域において、新しい分子の自己組織化現象の探索ならびに分子システムの構築にチャレンジしています。
分子システム化学においては、システムの構成要素間の相互作用を如何に静的・動的に制御するかが重要となります。すなわち、分子・分子集合体・ナノマテリアルの表面、界面の構造と性質がシステム設計において重要な意味をもちます。多様なナノ界面を創り出すためには、多様な構成要素を用いることが有効なアプローチであり、俯瞰的な視野からナノ化学における新しい問題に挑戦しています。
分子組織化に基づく光エネルギーの変換技術 I
・フォトン・アップコンバージョン分子システムの開発と応用
分子組織化に基づく光エネルギーの変換技術 II
・光エネルギーの分子貯蔵 (Solar Fuel)ならびに変換技術
ソフトイオニクスの開拓
・キラルな柔粘性結晶の開発ならびに指向性イオン輸送
ソフト界面イオニクス:イオン液体と分子集積化学、界面化学の融合
・イオン液体を媒体とする自己組織化現象
・イオン液体への界面(水、有機溶媒)の導入と新しい界面ナノ材料合成手法の開発
タンパク質中空カプセル、ナノスフィアの合成技術と機能
ナノ界面・空間における分子システム化学†
・空間的に構造制御されたナノ金属アレイ構造(ナノフィン、ナノボックス)を舞台
とする分子システム光化学
・巨大超薄膜(ナノメンブレン)技術の革新的展開
†九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所 藤川茂紀准教授との連携研究
金属錯体、金属・半導体ナノ粒子の分子組織化学
・金属錯体を主鎖とする自己組織性高分子錯体の化学―超分子強誘電体を目指して
・金属錯体による分子情報変換・増幅システムの開発
・ヘテロポリ酸の自己組織化によるナノシート形成と応用
・Metal-Organic Framework (MOF)の新しい機能材料科学
アダプティブな自己組織化
分子の自己組織化と非平衡科学の融合―散逸ナノ構造の形成と応用
フォトン・アップコンバージョン分子システムの開発と応用 (最近の総説はこちら1, 2)
フォトン・アップコンバージョンとは、低いエネルギーの光を高いエネルギーの光に変換するエネルギー操作技術です。これまで活用出来なかった低いエネルギーの光(近赤外光など)を高いエネルギーの光(可視光など)に変換できれば、太陽電池や水の可視光分解(水素エネルギー製造)をはじめ、太陽光の利用効率が飛躍的に向上する可能性があるため、世界中で活発な研究が行われています(Fig. 1-1)。

Figure 1-1. フォトン・アップコンバージョンの概念図
近年では、弱い励起光でもアップコンバージョン発光を観測できる三重項―三重項消滅(triplet-triplet annihilation; TTA)を経る機構が注目を集めています。このTTA機構によるアップコンバージョンでは、ドナー(増感剤)とアクセプター(発光体)をペアで用います。まず光を吸収して三重項励起状態(Figure 1-2)となったドナーがアクセプターに三重項エネルギー移動します。これにより生じた励起三重項にある2つのアクセプター分子が溶液中を拡散して衝突すると、そのうち1分子が三重項状態よりも高い励起一重項状態となり、この励起一重項状態から高いエネルギーの発光を発します(Fig. 1-3)。

Figure 1-2. 基底状態,励起(一重項,三重項)状態における電子スピンの配向模式図

Figure 1-3 TTA機構によるフォトン・アップコンバージョン(エネルギーレベル図)
このTTA機構によるアップコンバージョンでは通常、ドナー、アクセプター(発光体)として働く2種の色素分子を有機溶媒に溶解させます。まず光を吸収して三重項励起状態となったドナーがアクセプターに三重項エネルギーを移動し(TTET)、これにより生じた励起三重項にある2つのアクセプター分子が溶液中を拡散して衝突すると、そのうち1分子が三重項状態よりも高い励起一重項状態となり(TTA)、アップコンバージョン発光を発します。すなわち、低いエネルギーしか持たない2つの光子を用いて、より高いエネルギーの1つの光子を生み出すことになります。
これまでの研究では、ドナーとアクセプターを溶液やポリマーに分散させ、色素分子の拡散と衝突によりエネルギー移動を起こしていましたが、応用上重要な固体状態では分子拡散が制限される、励起三重項状態が酸素により失活するため空気中ではアップコンバージョンが起こらない、といった問題点がありました。そこで我々は、従来のような媒体中における色素分子の拡散衝突に基づくTTAを用いるのではなく、色素分子の分子凝縮系あるいは自己組織化系において、色素分子間の三重項エネルギーマイグレーションに基づく新しいTTAフォトン・アップコンバージョン分子システムを提案、開発しています(Fig. 1-4)。

Figure 1-4. (左)従来の溶液中、あるいはポリマーマトリックス中の分子拡散に基づくTTAアップコンバージョン。(右)自己組織化したアクセプター分子組織体内におけるエネルギーマイグレーションに基づくTTAアップコンバージョン(模式図)
【1】 分子凝縮系(π電子液体系)アップコンバージョン分子システム
室温で液体のアクセプター分子を用いることにより、揮発性有機溶媒を用いずにTTAフォトン・アップコンバージョンを達成できることを見いだしました(Fig. 1-5)。これは溶媒を含まないπ電子系液体でアップコンバージョンが観測された初めての例です。また、従来TTA機構によるフォトン・アップコンバージョンにおいては、励起三重項状態が空気中の酸素によって失活するという致命的な問題点がありましたが、分子凝縮(液体)系を利用すれば溶存酸素の存在下においてもアップコンバージョンが実現できることを明らかにしました。

Figure 1-5. 無溶媒π電子液体において初めてアップコンバージョン発光を観測
【2】 有機ナノファイバー中へのドナー・アクセプター分子のとりこみによるフォトン・アップコンバージョン
TTA機構によるフォトン・アップコンバージョンには、励起三重項が空気中の酸素によって消光されてしまう致命的な問題点がありました。そこで我々は、超分子ゲルファイバー中に色素分子を密に集積することで、空気中でもTTA-UC発光を発現できることを見出しました。超分子ゲルを形成する際にドナー、アクセプターを加えておくだけで空気中においてTTA-UCを観測でき、色素の種類を変えることで近赤外光から可視光、赤色光から緑色光、緑色光から青色光、可視光から紫外光への波長変換を達成しました(Figure 1-6)。

Figure 1-6 超分子ゲル中において初めてアップコンバージョン発光を観測 (J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 1887.)
【3】 アクセプター分子膜組織体
アクセプター分子に親媒部(アルキル鎖)と疎媒部(ジフェニルアントラセン発色団)を導入して自己組織性を付与することにより、理想的なアップコンバージョン系の構築に成功しました(Fig. 1-7)。このアクセプター分子を有機溶媒に溶解すると、自然に自己組織化して安定な分子膜を形成し、そのアクセプター分子膜中にドナー分子が効率よく取り込まれるための条件を明らかにしました。その結果、フォトン・アップコンバージョンを示す自己組織化分子システムを世界で初めて開発し、そのアップコンバージョン量子収率は30%と極めて高いことが明らかとなりました(2つの光子を1つの光子に変換する過程のため、理論上の最大効率は50%)。また、アクセプター分子膜中においては、アクセプター基が高密度に配列しているため、励起三重項エネルギーが高速に動き回り、ふたつの励起三重項エネルギーが効果的に出会うことが判りました。その結果、太陽光程度の比較的弱い光(励起光強度)でアップコンバージョン過程を最適化することに成功しました。更に興味深いことに、分子膜中に導入された水素結合ネットワークは、酸素(溶存酸素)に対してバリア能を有し、酸素が存在してもアップコンバージョン発光がほとんど保たれる画期的な特徴を有することが明らかとなりました。

Figure 1-7 自己組織性アクセプター分子膜中のエネルギーマイグレーションを利用する高効率TTAフォトン・アップコンバージョンシステム(Scientific Reports., 2015, 5, 10882.)
光エネルギーの分子貯蔵 (Solar Fuel)ならびに変換技術
光エネルギーを分子の光異性化を利用して分子に貯蔵し,必要に応じて熱量として取り出す技術(Solar thermal fuel)は,古くはノルボルナジエンやアゾベンゼンの光異性化現象、また近年ではジテニウム錯体などを対象として研究がすすめられてきました(Fig. 2-1)。 このように、光エネルギーを分子に蓄えるSolar fuelには、高いエネルギー密度が望まれ、このためには、溶媒で希釈しない固体あるいは無溶媒液体材料系が望まれます。 一方、例えばアゾベンゼンのtrans→cis光異性化は、固体結晶中では一般に抑制されることから、従来の光異性化現象の多くは、溶媒で希釈した溶液状態において検討されており、エネルギー密度を高めることは困難でした。

Figure 2-1 分子への光エネルギー貯蔵と熱エネルギーの取り出し:Solar thermal fuelの概念
【1】π電子系液体Solar fuelの開発
そこで、分岐アルキル鎖を導入したtrans-1を開発しました。この分子は室温で液体状態にあり(ガラス転移温度:-63℃)、紫外光(365 nm)と可視光(480 nm)の光照射により可逆的にtrans ⇄ cis異性化することが判りました。このとき cis-1に蓄えられるエネルギー ΔH は 52 kJmol-1であり、無溶媒液体系とするアプローチにより、thermal batteryとして必要とされるエネルギー密度(31 kJ mol-1 = 100 J g-1) を満足することができました(Fig.2-2)。

Figure 2-2 π-Liquid thermal molecular fuel (Chem. Commun, 2014, 50, 15803)
【2】イオン結晶―イオン液体間のフェーズクロスオーバー(phase crossover)化学
Solar thermal fuelにさらに高いエネルギー密度を与える新しい指針として、イオン結晶 ⇄ イオン液体間の相変化に基づく潜熱を導入すべく分子2(n、m)-Xを開発しました。 短いアルキル鎖長 (n,m)を有する 2(1,2)-Cl, 2(1,4)-Cl 及び嵩高いTf2Nを対アニオンとして持つ 2(6,4)-Tf2N は室温でイオン液体(IL)ですが、2(4, 6)-Br, 2(6, 4)-Br, 2(8, 2)-Br 及び 2(6, 4)-Br はイオン性結晶(IC)として得られました。trans-2(6,4)-Br(IC)は紫外光照射すると液化し、cis-2(6,4)はイオン液体(IL)でした。一方、cis-2(6,4)に可視光照射すると、可逆的に光結晶化することが判りました。ここで興味深いことに、cis-2(6,4)(IL)を加熱すると、trans-2(6,4)(IC)への熱異性化とともに結晶化し、この時の発熱量ΔH = 97.1 kJ mol-1はcis体のアゾベンゼン発色団に蓄えられる熱エネルギー(ΔH~50 kJ mol-1)の約2倍でした(Fig.2-3)。

Figure 2-3 光誘起イオン結晶―イオン液体相転移とSolar Thermal Fuelへの応用 (Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 1532.)
このように光融解するイオン結晶系においては、cis体に蓄えられるコンフォメーションエネルギーに加えて、イオン液体―イオン結晶間の相転移 [cis-2(6,4)(IL)→trans-2(6,4)(IL)] → trans-2(6,4)(IC)に伴う潜熱を蓄積できることが判りました。またtrans-2(6,4)(IC) ⇄ cis-2(6,4)(IL)の可逆的な光相転移に伴い、イオン伝導性が2桁変化することが確認されました。このように光相転移を利用して複数の凝縮系機能を同時に制御することが可能であり、Phase Crossover Chemistryの概念を提案しています。
キラルな柔粘性結晶の開発ならびに指向性イオン輸送
Coming soon...
ソフト界面イオニクス:イオン液体と分子集積化学、界面化学の融合
イオン液体は、室温で液体状態にある溶融塩であり、常温常圧下では不揮発性であること、他の媒体との相溶性を制御できるなど、これまでの有機溶媒にない特徴を有しています.イオン液体を媒体とする触媒反応、高分子合成反応や電気化学については、多くの研究がなされています。
一方、私たちは、生体高分子を溶解するイオン液体の開発、ならびにイオン液体中における自己組織化現象に関する研究を1999年に開始しました。ハライドアニオンを有するイミダゾリウム塩が、糖、多糖や糖誘導体を溶解することや、アガロースによるイオン液体のゲル化(イオノゲル形成)を世界で初めて報告しました(Fig.4-1)。また、適切にデザインした糖脂質分子がイオン液体中においてナノファイバーを形成し、イオン液体をゲル化することもはじめて見出しました(Fig.4-2)。イオン液体中における二分子膜形成を糖脂質以外にも一般化し、秩序性分子組織体が得られることを確立しました。
次に新たな展開として、イオン液体中における界面の導入と、界面材料化学の展開を進めています。例えば、イオン液体中に導入したミクロ界面を利用する中空型金属酸化物(TiO2など)の一段階合成(Fig.4-3左)や、極薄金ナノシートの合成手法(Chem.Lett. 2005, 34, 1234.) を開発しました。
さらに、イオン液体と水のなす界面を利用した生体高分子(タンパク質・多糖)マイクロカプセルの作製にも成功しています(Fig.4-3右)。タンパク質を素材とするカプセルにおいては、内水相に核酸や酵素タンパク質を導入することができることから、天然素材カプセルとして様々な応用が期待されます。


Figure 4-1 ハライドイオンを対イオンとするイオン液体中における糖の溶解と
多糖イオノゲル
N. Kimizuka, T. Nakashima, Langmuir, 2001, 17, 6759.
T. Nakashima, N. Kimizuka, Chem.Lett. 2002, 31, 1018.

Figure 4-2 糖脂質によるイオン液体のゲル化と二分子膜形成
イオン液体を媒体とする分子の自己組織化,イオノゲル形成の最初の報告.
N. Kimizuka, T. Nakashima, Langmuir, 2001, 17, 6759.
T. Nakashima, N. Kimizuka, Chem.Lett. 2002, 31, 1018.

Figure 4-3 イオン液体中へのマイクロ界面の導入と金属酸化物中空粒子の一段階合成(左),タンパク質中空カプセル合成(右).
T. Nakashima, N. Kimizuka, JACS, 2003, 125, 6386.
イオン液体―水マイクロ界面におけるタンパク質マイクロカプセルの形成は、カチオン性イミダゾリウム塩からなるイオン液体と水の界面において、アニオン性のタンパク質が静電的に吸着し、集積されることを意味しますが、このことは、イオン液体が動的な担体(mobile molecular substrate)になることを示唆しました。そこで、単分散コロイド粒子の水―イオン液体界面における集積挙動を共焦点レーザー顕微鏡ならびにSEM観察を用いて検討しました。その結果、イオン液体がmobile supportとなり、無機コロイド粒子についても密な界面集積を達成しました(Figure 4-4)。

Figure 4-4. イオン液体―水界面における無機コロイド粒子の二次元組織化
ナノ界面・空間における分子システム化学
Coming soon...
金属錯体、金属・半導体ナノ粒子の分子組織化学
・金属錯体を主鎖とする自己組織性高分子錯体の化学―超分子強誘電体を目指して
・金属錯体による分子情報変換・増幅システムの開発
・ヘテロポリ酸の自己組織化によるナノシート形成と応用
・Metal-Organic Framework (MOF)の新しい機能材料科学
金属錯体は、金属元素の多様性と有機配位子の設計自由度を併せ持つことから、機能材料の優れた構築素子といえます。私たちは、脳神経(ニューロン)における自己組織化現象(Fig.5-1)をヒントに、一次元金属錯体を主鎖とする自己組織性ナノワイヤーの創成に取り組んできました。
究極のバイオコンピューターである脳は100億個のニューロン(神経細胞)からなると言われていますが、この神経回路における素子間の結合は、外からの刺激(学習)に応じた構造変化によって制御され、またこれらを構築する分子素材は代謝により絶えず作り替えられています(刺激応答性、学習機能、代謝・再生機能)。神経細胞は軸索(axon)と無数の樹状突起(dendrite)をもち、神経系のもつ可塑性は、細胞間の生体分子認識を基礎とする回路網の動的な形成によりもたらされています。ここで、軸索はミエリン鞘とよばれる脂質やタンパク質からなる分子組織体で被覆されています(Fig.6-1)。神経における興奮や伝導性の直接の担い手となるのは神経の細胞膜であり、軸索の一部に膜興奮が起こると、これにより生ずる脱分極は次々と隣接部に伝わってゆきます(伝導)。ここでミエリン鞘による被覆絶縁化がインパルスの高い伝導速度を達成するために必要と考えられています。このような脳の神経回路網の自己組織化に学び、動的に構築される人工素子やその回路網形成を、様々な分子素材を用いてボトムアップ(bottom up)にデザインすることは、新しいナノ材料の創出に繋がると期待されます。例えば電子的に共役したナノワイヤーを自己組織的に構築できれば、neuromorphilicな機能ネットワークデバイスを設計するための基礎となるでしょう(Fig.6-2)。
一次元金属錯体は、一次元系に特有の電子状態や物性を示すことから、固体物性科学において構造と物性の相関が調べられています。これらは固体の中の単位構造として存在しますが、この一次元鎖を溶液系に取り出してナノワイヤーあるいは高分子として操作することができれば、従来にない自己組織性ナノ材料の創出と機能展開が可能になるものと期待されます(Fig.6-3)。
私たちは、一次元金属錯体の構造を溶液系で保つために、両親媒性を付与する新しい方法論を開拓しました(Fig.6-3, 6-4)。これにより、従来固体状態でしか存在しなかった一次元錯体を溶液に分散させることに成功しました。また、溶液系においては、超分子サーモクロミズム、超分子バンドギャップ工学、疎媒性収縮による低スピン型金属錯体の安定化、動的なスピンコンバージョンなど、従来の固体系錯体化学では知られていない新しい現象や機能を次々と見出しています。すなわち、金属錯体の電子物性、スピン状態や光機能などの物性は、ナノレベルの自己組織化現象と融合することにより、ナノ界面の特徴を示すことが明らかになりつつあります。

Fig.6-1 神経細胞と軸索,ミエリン鞘の構造
神経細胞は軸索(axon)と無数の樹状突起(dendrite)をもつ.軸索はミエリン鞘とよばれる脂質やタンパク質からなる分子組織体で被覆されている.軸索に生ずるインパルスは次々と隣接部に伝わってゆくが(伝導)、ここでミエリン鞘による被覆絶縁化はその高い伝導速度を達成するために必要である.(Molecualr Biology of the Cell, 3rd ed.改変)

Fig.6-2 自己組織性を有する電子共役型一次元錯体(分子ワイヤー)の概念

Fig.6-3 擬一次元ハロゲン架橋白金混合原子価錯体脂質複合体溶液中における自己組織性ナノワイヤーの形成と超分子サーモクロミズム

Fig.6-4 脂溶性一次元金属錯体の示すユニークな特性の一例
Reviews
1)N. Kimizuka, “Self-Assembly of Supramolecular Nanofibers”, Adv. Polym. Sci., 2008, 219, 1-26.
2) N. Kimizuka, “Soluble Amphiphilic Nanostructures and Potential Applications”,
In Supramolecular Polymers, 2nd ed. Ed by A. Ciferri, Taylor& Francis, Boca Raton, Chapter 13, 2005, 481-507.
3) 君塚信夫,“金属錯体を主鎖とする自己組織性ナノワイヤーの設計と動的機能”, 未来材料,2006, 6, 35-43.
アダプティブな自己組織化
生命分子そのものを構成要素としてナノ構造を構築できれば、生命分子に内在する分子情報や機能を備えた、新しいタイプの分子組織体が得られるものと期待されます。核酸やペプチドなどの生体高分子を構成要素とする自己集合は、既に多くの研究がなされています。一方、自己組織性を有しない生命小分子をナノ集積構造の構成要素にできれば、バイオナノ材料として新しい展開が可能になるものと期待されます。そこで、分子単独では自己組織性を示さないモノヌクレオチドやアミノ酸などの生命小分子を構成成分とし、それらと特異的に相互作用する分子を網羅的に探索する「分子ペアリング手法」を提案し、ナノファイバー構造が自発的に得られることを明らかにしました(Fig.7-1)

Figure 7-1. 生命小分子の自己組織化によるナノファイバー形成
M.-A Morikawa, N. Kimizuka et.al. JACS, 2005, 127, 1358.
T. Shiraki, M.-A. Morikawa, N.Kimizuka, Angew. Chem. Int. Ed., 2008, 47,106.(Hot Paper)
従来のホストーゲスト化学においては、最初にホスト分子(超分子)が設計され、そのホストのサイズに適合するゲストに対して選択的な結合がおこるというアプローチで研究が進められてきました。一方、このアプローチの限界は、タンパク質やナノ粒子などの、大きく、かつ非対称構造を有するナノマテリアルを認識する巨大ホストの開発が困難な点にあります(Fig. 7-2)。

Figure 7-2. 従来のホストーゲスト化学(超分子化学)とその限界
そこで、生命小分子の自己組織化アプローチは、生命分子と金属イオンの組み合わせに拡張しました。水中において、ヌクレオチドと希土類イオンからアモルファスの配位ネットワークから成るナノ粒子が形成されることが判りましたが、興味深いことに、様々なサイズや形状を有する分子、ナノ粒子、タンパク質が共存すると、これらに対して適合包接現象を示すことが明らかになりました。我々は、この適合包接現象を”Adaptive self-assembly”と呼び,新しいパラダイムの創出ならびに応用をはかっています。このランタニドーヌクレオチド系ナノ粒子の研究において、アニオン性Pt(II)ポルフィリンが配位ネットワークに取り込まれると、溶存酸素が存在するにもかかわらずリン光を発することが判りました(Figure 7-3)。すなわち、配位ネットワークは緻密であり、酸素分子をブロックする性質があることが判ります。この分子ネットワーク構造による酸素ブロック効果の発見は、我々のグループにより展開されている自己組織化フォトン・アップコンバージョンの研究に活かされています。

Figure 7-3. ヌクレオチドーランタニドイオンによるAdaptive Self-assembly
R.Nishiyabu, N.Kimizuka et.al., JACS, 2009, 131, 2151.

Figure 7-4 ヌクレオチドーランタニド配位ネットワークによる酸素ブロック能の発現
(分子組織化により、酸素に不安定な励起三重項状態を安定化できる)
分子の自己組織化と非平衡科学の融合―散逸ナノ構造の形成と応用
自己集合(self-assembly)は、静的な自己組織化(static self-assembly)と動的な自己組織化(dynamic self-assembly)の2つに分類される。前者は熱力学的平衡近傍での自己集合であり、後者は熱力学的平衡から遠い条件で物質が自発的にパターンや構造体(散逸構造)を形成するもので、TuringパターンやBernerd対流をはじめとするマクロな構造形成現象が知られている。従来の分子集合化学や超分子科学は前者の熱力学的平衡、すなわちstatic self-assemblyを拠り所として発展してきた。一方、細胞内の生命現象は、細胞膜という界面に支配された非平衡化学系を舞台としながら、分子認識などの熱力学的平衡現象を要素とする分子システムから成り立っている。ここで、非平衡状態を舞台とする分子の自己組織化が、どのような特徴を有するのか明らかにし、さらにその物質科学的な展開をはかることは、化学における未踏分野のひとつである。特に、非平衡状態(あるいは未平衡状態)における動的な自己組織化プロセスを利用し、熱力学的平衡状態においては得られない特異な形状や性質を有するナノ構造・材料を構築するための方法論を開拓することは意義があろう。このためには,エネルギーあるいは物質の流れの中でのみ形成される秩序構造“dissipative nanostructure”を見いだすことが出発点となる(Figure 8-1)。

Figure 8-1. Static self-assembly と Dynamic self-assemblyにおけるスケール
非平衡状態における分子の自己組織化を探求するためには、液―液界面を介した分子の拡散(流)と分子集積化現象を組み合わせるアプローチが考えられる。我々は、非平衡条件における金属錯体の動的自己組織化を利用したナノ材料開発という観点から、水―有機溶媒界面におけるAu(OH)4–錯体の構造形成について検討した。興味深いことに、Au(OH)4–錯体水溶液と脂溶性アンモニウム塩のクロロホルム溶液のなす界面に紫外光を照射すると、発達した金ナノワイヤーが形成された(Figure 8-2)。予め両相を激しく攪拌して熱力学平衡に達せしめた後に光照射すると、金ナノ粒子しか得られない。すなわち、水―有機界面で形成されたAu(OH)4–/脂溶性アンモニウム塩のイオン対が、濃度勾配を駆動力として水相へナノワイヤー状集合体として生長し(散逸ナノ構造)、この構造が界面近傍で光還元されて金ナノワイヤー構造を与えたものと考えられる。この結果は、ナノレベルの散逸構造が存在することを示している。

Figure 8-2. 液―液界面におけるナノレベル散逸構造(散逸ナノ構造)の発見
T. Soejima, M-a. Morikawa, N. Kimizuka, Small, 5, 2043 (2009).
従来、静的な自己組織化(static self-assembly)は化学や生物学において、熱力学平衡支配の分子組織化現象として研究されてきた。一方、非平衡条件下における動的な自己組織化(dynamic self-assembly、 self-organization)は、巨視的な構造形成現象であり、物理学の研究分野であった。今回、ナノレベルの散逸構造は、非平衡条件下における分子のstatic self-assemblyによってもたらされており、非平衡科学における新しい研究領域を拓くものと位置づけられる(Figure 8-3)。

Figure 8-3 散逸ナノ構造のstatic self-assembly、 dynamic self-assemblyとの位置づけ
散逸ナノ構造の概念は、巨視的な液―液界面における非平衡条件を背景とする分子の自己組織化という新しい視点を与えるものであるが、一方、均一系においても非線形性のある自己組織化プロセスは顕在すると考えられた。
我々は、金ナノ結晶の形成を “酸化還元反応を伴うAu3+イオンの動的自己組織化”という視点で捉え、Au(OH)4‒錯体の還元による集合反応と酸化溶解の2つのプロセスを同時に行った。金属ナノ結晶においては、結晶面における性質(反応性)が異なるために、その界面における化学平衡現象に非線形性・協同性が発現する可能性があるためである。その結果、ナノプレートにナノサイズのクレバスが入った花冠状やプロペラ状構造など、特異な構造を有する単結晶金ナノプレートを合成することに成功した(Figure 8-4)。

Figure 8-4 金属ナノ結晶の形成を、ナノ界面の性質を反映した自己組織化現象と捉えることにより、特異なモルフォロジーを有する金ナノ結晶の形成に成功。